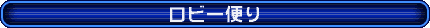

「一撃必殺アプサラス仮面2・愛と悲しみの激闘編〜兄(あん)さん、動いたらメギドやで〜」…という前向きかつアグレッシボゥなタイトルはどうでしょうか!?」
俺は視線をその言葉の主…虚華(うつか)に向け、肺にためていたタバコの煙を吹き付けた。
「ハァー!? またリテイクですか!? これで6度目ですよ!? アナタはリテイクの国からやってきたリテイク王ですか!? ええ!?」
「仮面2っていうけどな…2って何だよ、2って」
「2は2ですよ! ツゥ! 英語で二!」
こいつが男だったら、もう殴っているだろうな。蹴りも入れているかもしれない。まぁそれはともかく…何故俺が、こんな人気のないロビーで、この難解思考女・高天(たかま)虚華と一緒にいて、色々と騒いでいるかと言うと…それは…。
「ダッシャア! これでどうですかお客さん!」
「るせー! 今さっきの質問に答えろ!」
「2?」
「2だ」
俺は虚華が差し出してきたフリップをとりあえず受け取りながらも、聞いた。こいつは放っておくと、いつまでも答えないからだ。
「いや、ほら…エピソード2?」
「じゃあ「一撃必殺アプサラス仮面エピソード2〜」でいいじゃないか」
「長いじゃない」
「元から長ぇんだよ」
虚華は髪の毛をいじりながら、何か考え込み始めた。どうせロクなことじゃないだろうが、待つ事にして、俺はフリップを裏返した。
「「神出鬼没アプサラス仮面2・血と汗の黙示録 〜ミルリリーの花言葉は即死〜」…」
俺は迷わずフリップを投げ捨てた。
「ああ!? ていうか何してんの!?」
当然無視だ。こいつと論議してる時間が勿体ない。
「いいか虚華、お前が言い出した事なんだからな。俺は忙しい
中、それに協力してやってるんだ。これ以上ワケわからねぇタイトル考えるなら、俺は帰ってテレビ見ながら寝るぞ」
「…最後のくだりが矮小(ミニマム)な感じだけど…わかったよぅ。じゃあ一番最初に考えていたタイトルで、いいかな」
一言余計だが、しおらしくなった。こいつは黙っていれば至極俺好みの美人だから、まぁ、それは関係ないけど、とにかく聞くことにする。
「どんなだよ?」
「「風の行方」…」
発端はこうだ。
停滞ムードの漂うパイオニア2では、そのムードを払拭すべく、様々な催しが開かれていた。体育大会みたいなものもあれば、様々な展示会、品評会、ディスカッション(明るい話題のもの)、ミスコン等が主だが、もっと文化的なものもあった。
民衆の不安や倦怠を、少しでも明るくしようと、様々な分野(と言っても制限はあったがな)でのシナリオを広く募り、それをドラマ化、つまり映像にしようという企画である。
お笑いやら、ラブストーリー、感動のドキュメント、痛快なアクション等のシナリオを書いてしかるべき所へ送り、それが審査を通れば、一流のスタッフと役者により映像化されるというわけだ。
まぁ、そんなんで暗い雰囲気の根本的な解決になるとは思えないが、どういうわけか、虚華はそれに食いついたのだ。
「やっぱねぇ、文明っつぅのは文化があって初めて成り立つんですよ」
俺は自慢じゃないがそういった分野にはまるで暗いので、虚華のその言葉が正しいのか間違いなのかはわからない。
だがまぁ、反対する理由もなし、それに手伝いくらいならと、そういうわけで、高天大先生の執筆作業を手伝っているという次第だ。
「タイトルはまぁそれでいいんじゃないか。ジャンルは?」
俺は食料制限で全く甘くないコーヒーをすすりながら、そう聞いた。どこをどうすれば「風の行方」が「アプサラス〜」になるのかは判らないが、そこはもういいだろう。ありがちなタイトルだが、他よりはマシだ。
「んー…今は、島で何か起こってて…下に降りられないワケでしょ? その前…ダークファルスを倒すまでの話を、簡潔にまとめるっていうか」
それでアプサラス仮面2だとかどうとかぬかしてやがったとは…侮れない女だぜ。そこがいいんだけどな。
「そんで…大筋は…謎のセクシーフォマール・アプサラス仮面が、エネミーをちぎっては投げ、ちぎっては投げ…」
なるほど…興味深い…展開…あれ?
「更にはライバルのマスク・ド・ヴァラーハが物語を否が応にも盛り上げ…恋人のマスクマン・ミスターガルダとのロマンス…」
「ちょっと待て! 今の所、登場人物が100%マスクマンなんだが!?」
「ちょっとちょっと、揚げ足とらないでくれる? これからいい所なんだから…で、謎、かつ悪の手先、マスク・ザ・ナンディンが登場し、圧倒的な火力でアプサラス仮面とミスターガルダを追い詰めるのね…で、あわや! という所で、ライバルのマスク・ド・ヴァラーハが現れて、助けてくれるんだけど…相討ちになっちゃうの…ヴァラーハは、実はアプサラス仮面の生き別れの父という泣かせる設定で…」
きりがない。放っておけばずっと喋り続けるだろうから、俺は虚華を制し、何とか落ち着かせた。ダークファルスとも絡んでないし。
「わかった。わかったよ。その先は原稿用紙に頼むぜ。それと、一人くらいは素顔の奴を出してやれ」
「マスクマンが仮面を外すのは、ゴハンの時とお風呂入る時だけですよ」
「…」
先行き不安だが…。
それから数日後。
「エグゼぇ! 大変大変!」
虚華の住むマンションの1階にあるオープンカフェで、まったりしていた俺の所へ、慌しく走ってくる虚華の妹、逸華(いつか)。
「どうした?」
「お姉ちゃんがおかしくなった!」
普通なら、不安か、それに近い表情をするだろうが、逸華のそれは、むしろ期待だった。
わからないでもないが。
「あれ以上はおかしくならないだろうよ」
「いやぁ、それがねぇ…一升瓶片手に、白人の真似しながら謎の歌を唄うという、かなりアグレッシブな状態ですよ?」
一升瓶片手…白人のマネ…謎の歌…。
「行くぞ逸華!」
「アイアイ、サー!」
ドアを開けた瞬間、本当に瞬間、虚華が飛び出してきて、一升瓶で殴りかかってきたもんだから。
身の危険を感じた俺は、迷うことなく、虚華にボディブローをかまし、気絶させようとしたわけで。
実際そこまではうまくいったわけで。
「……!」
誤算というか、まぁ、当然というか…。
そりゃ、知らない仲じゃないし、むしろよく知ってる仲だし、遠慮はお互いにないんだが。
「だからってゲロ吐くんじゃねええぇよ!」
「うぅ…私はもうダメよ…私が死んだら、ミルリリーの咲き乱れるお花畑に手厚く葬って頂戴ね…」
「近づけねぇよ。あー、逸華、タオルくれ…」
反応がない。見ると、呼吸困難を起こして床に這いつくばっている。
「笑い過ぎだぞてめぇ!」
シャワーを浴び、さっぱりしてから、二人の元へ行く。まったく、散々な目にあった。初体験だ。
「いやぁ、ビデオ用意しとかなかったのは失敗だったねぇ」
「あのなぁ…」
「ごめんなさい…」
酔いが醒めた虚華が、縮こまって俺を見上げる。
「ま、それに関しては後々ペナルティを課すとして、だ。どうなんだ? 酒かっくらってハイになって、何か書けたのか?」
「概要っていうか、方向性は見えました」
「ほぅ…」
虚華はそれだけいうと、何やら言いたげに、俺に視線を送ってくる。無碍にしても仕方ないので、聞くことにした。
「なんだ?」
「取材に行きたいのですが」
「しゅ…ざい? 取材? それって漫画家が原稿間に合わない時の言い訳じゃあないのか?」
偏見な気もしないでもないが。まぁ俺の「取材」に対する考えなど、その程度である。
「馬鹿な…エグゼ・ヴェルマッハともあろう御方の発言じゃあありませんね。取材してきた要素をフルに活かし、スゲェイカス内容のシナリオを書き上げれば、ありとあらゆる年齢の支持を得ること請け合い。8馬身差くらいで入賞し、即映像化され、皆様に夢を与えます。そしてその見返りとして、銭が。メセタが。あと名声と地位も」
最後の方でかなりアレな感じの本音が出たが、言わんとしている事はわかった。ここは言う通り、取材に行かせてやろう。
「よし…いいだろう。何処に行くかは知らんが、存分に取材してくることだ。ただし期限は三日! それ以上かかった場合は、1日につき印税10%を俺に回すこと」
「…取らぬ狸の川津掛け(かわづがけ)って知ってる?」
知らないな。 |
|

